子育て中の皆さんお疲れ様です。
イクメンシリーズの3回目ということで、今回は1歳ごろ~3歳ごろまでの幼児編です。
幼児期になると自分で考えて行動することが出来るようになり、好き嫌いなども増えてくる時期ですが、成長が著しいこの時期には父親の関わり方も非常に重要です。
どのように幼児期の子供やママと接していくとよいのかについて、解説していきます。
目次
1.発達段階を理解しよう
まず、子供の発達段階をしっかり理解する必要があります。
子供が今何をできるようになるのか基準を知ることで、自分の子供へのフォローのやり方も変わっていきます。
幼児期はとくにできるようになることが多く、ママやパパのフォロー次第でも成長が変わってくる時期でもあります。
イクメンを目指すうえでも、この時期の発達段階を知っておくことは子供への接し方やパートナーの対応を理解するうえでも非常に重要です。
この頃にできるようになることをざっくりと紹介します。
子供の現状を知っておく
子供の年齢ごとの発達段階も大切ですが、合わせて自分の子供が何が出来て、何が出来ないのかを把握しておく必要があります。
現状を知るためには、パートナーに教えてもらうために時間を設けること、子供との時間を増やしたり観察できる状況を作ることが非常に重要です。
もしも今まで仕事などで時間が作れていなければ、子供の現状を知るために保育園などの連絡帳を見るなど簡単なことからでも、「今から」始めてください。
発達に関しては、発達段階の年齢でできることが出来ていなくても、焦る必要もありません。
成長には個人差もありますし、ある日突然上手にできていることもあります。
現状を知ることで、子供が苦手なことでも楽しめるようにフォローしてあげたり、もしもそのことでパートナーが悩んでいたら、一緒に話し合って解決できるようにしましょう。
2.パートナーと育児の方針を話し合う
子供へのNG対応の1つとして挙げられるのは、ママとパパで方針が異なることです。
「ママにはこう言われたけど、パパは違うことを言う」となると子供は混乱してしまいます。
今まであまり育児に関わっていなければ、パートナーの努力を無駄にしてしまうこともあります。
パパが子供に甘ければ、「楽だから」という理由で子供もパパの言うことを信じやすくなり、今まで頑張ってきたママとしてはすごく迷惑な話になってしまうため、育児の方針を知るためにも話し合いが重要です。
育児方針の話し合いについては下記の記事でも解説しているので参考にしてみてください。
▶【意外と知らない】子供が混乱する?ママとパパでの子育て方針の違い
話し合いのポイント
この話し合いの際にポイントとなるのは、育児の中心にいるパートナーの話をよく聞くことです。
パートナーの話を否定するのではなく、頑張ってくれているパートナーを労いながら尊重し、自分なりに「こうしたい」と思いがあれば、しっかり意見を伝えて話し合いましょう。
もしも、パートナーの育児の方針が客観的に見て一般常識から悪い意味で逸脱している場合は、パートナーが納得できるように何度でも話し合うことをおススメします。
3.地域の子育てサロンやイベントに参加する
地域の子育てサロンやイベントなどが、開催されている時に参加をしてみましょう。
同じ年齢ぐらいの子供たちが集まり、ママやパパがどのように子供たちと接しているのかを知る良い機会になります。
イベントにとよっては保育士や保健師など頼れる方々に相談できる場合もあるため、育児に今まで参加しておらず、育児についての経験が浅い場合はおススメです。
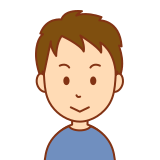
子育てサロンやイベントに参加する場合は、運営者の情報や口コミをしっかり確認しておきましょう。
少数ですが悪質なところだと物販や勧誘などもあるため、注意してください。
ちなみに筆者は最初の参加で巻き込まれた経験があります。
4.自分なりの子供への接し方を確立する
子供への接し方として、無理をしていてもいつかぼろが出てしまうのは当然のことです。
そこで自分なりの接し方を考えておく必要があります。
ここでの「自分なり」とは「子供や家族のため」の「自分なり」で自分が楽な方に流れるためではないことだけはしっかり覚えておきましょう。
すべての過程をパートナーのやり方に合わせるではなく、アプローチは違っても結果として同じ場所にたどり着けていればよいのです。
育児の方針は違えず、パートナーの努力は無駄にしないけれど、あなたらしさを出した育児が出来るようにしてみてください。
もしも「これでいいのか」と思ったら、パートナーや周りに相談したり、パートナーから指摘があったらしっかり話し合うなど、柔軟な姿勢を示しておくことで、きっと子供やパートナーからも受け入れられるでしょう。
5.子供の衣服のサイズを把握する
この時期は服や靴などもすぐに買い替えが必要になります。
服や靴の整理が追い付かず、サイズアウトしたものがまだ捨てられていなかったり、入れ替えられていなかったりする場合もあります。
子供がサイズアウトした服を着たり、着せたりしないように注意しましょう。
子供の服や靴のサイズを把握して、パパが整理をできるようにしたり、今着ている服がサイズアウトしそうなら買い足しをパートナーとも相談してから買いましょう。
保育園に通っている場合は、園にストックしている分もしっかり把握しておきましょう。
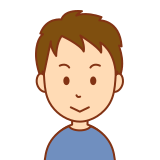
特に靴のサイズには要注意です。
指先が詰まりすぎていたりサイズが大きすぎてもケガや成長を阻害する要因になってしまいます。
足のサイズはしっかりお店に行って図ってもらいましょう。
また、靴自体もメーカによりつま先の幅が狭かったり、土踏まずが合わないなどもあるので、お店で試着してから買う方が安心です。
6.子供と遊ぶときはパートナーにはできない遊びを
パパは子供と遊ぶときにどのような遊びをしていますか。
1~3歳ごろでは、お散歩以外にも公園で簡単な遊具やボール、お砂場遊びなど外で遊ぶ方法がどんどん増えていきます。
普段ママが子供と一緒に遊んでいるならば、パパが遊べるときには外で肩車をしてあげたり、一緒にアスレチックをやるなど、普段ママとはできない遊びを経験させてあげるとよいでしょう。
そうすることで、遊びの幅が増えていろいろなことに挑戦したり、考えるきっかけにもなり、子供にとってプラスになります。
ママやパパのいずれか一人だけで、遊びの幅を増やすのは大変難しく、労力もかかるため負担が大きくなってしまいます。
ママとパパそれぞれが昔やった遊びを子供に教えたり、手先が器用ならそれを活かした遊びを教えてあげるなど、それぞれが出来る方法で子供と遊んであげましょう。
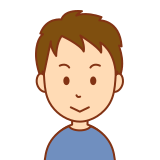
せっかくの休日だから家でゆっくりしたい気持ちは筆者もすごくわかりますが、休んでいる間パートナーに負担がかかりますし、子供もせっかくの休日なのにパパが遊んでくれないのは悲しくなるはずです。
時間を決めて遊んだり、子供とのお昼寝の時間を作るなどの工夫で対応していきましょう。
7.食べられないモノを把握しておく
この時期は離乳食から大人とあまり変わらない食事へと徐々に変わっていく時期でもあるため、外食がしやすくなったり、食事に気を遣うことが少なくなると思います。
しかし、年齢的なモノやアレルギーなどの体質的に食べられないモノはあるため、その把握はしっかりしておかないと最悪命に関わる場合があります。
また、食べれないものをしっかり把握しておかないと、パートナーも安心してパパに子供を見てもらうことはできないでしょう。
過去に食べられない食材をまとめていますので、参考にしてみてください。
▶【0~3歳】知っておきたい!避けるべき食材
8.日々のルーティンを把握しておく
子供の日々のルーティンを知っていますか?
起床、朝食、登園、お昼、お風呂、夕ご飯、就寝の時間や、寝る前に絵本を読んだり、何時間おきにトイレに行くことを促すなど、子供の様子を聞いただけではわからないルーティンがほとんどの場合存在します。
一見細かいと言われるかもしれないルーティンですが、トイトレだったり夜寝やすくするためだったり、睡眠時間の確保や睡眠の質を上げるために必要だったりします。
今まで育児をしていないと煩わしく思ったり、一日ぐらいと思いがちですが、このルーティンもパートナーや子供の努力だったりする場合もあるため、育児に関わるならしっかり把握しておきましょう。
把握したうえで、改善案があるならしっかり話し合ったうえで、導入をするようにして、独断でいきなりやってみることは避けてください。
9.時間を確保する
育児をしていると自分の時間を確保するのが、非常に困難になります。
平日であれば子供が寝静まって、残った家事を済ませ、翌日の準備が終わった後には疲れ切っているので、自分のことをやる時間はわずかになってしまいます。
そんな中、曜日ごとに寝かしつけから残りの家事を分担しておいたり、家電を買いそろえて負担を減らしておくなどして、自分とパートナーの時間をしっかり確保するようにしましょう。
共働きで平日は仕事で育児をするタイミングが少ない場合は、休日はパパが中心に育児をするなどよく聞きますが、それだとパパは休日がなくなり、反対にママが休日までずっと育児をしていると、ママが休めなくなってしまいます。
その気がなくても、どちらかに負担を押し付けてしまう結果になってしまうこともあるため、休日はどちらが育児の中心になるのか決めて、交互に休めるようにできると理想的です。
まとめ
仕事も育児も休息と適度なストレス発散がなければ、鬱やノイローゼになってしまったり、効率や質も下がってしまうのも事実です。
そのため、育児を分担して負担を分け合ったり、困ったときに助けたり、支えあえるようにするのが家族だと筆者は思っています。
育児は肉体面もですが、精神的な負担が非常に大きいと考えています。
1~3歳ごろでは大人と違い言葉をしっかり理解して行動に移せませんし、自分の興味関心を優先して行動するため、イライラしてしまうことも多くあります。
育児を知り、1人でも対応できるようになって、パートナーの負担を分散して、共感することが出来て初めてイクメンになれるのだと思います。
ママだけの育児ではなく家族での育児にするための参考にしてみてください。

