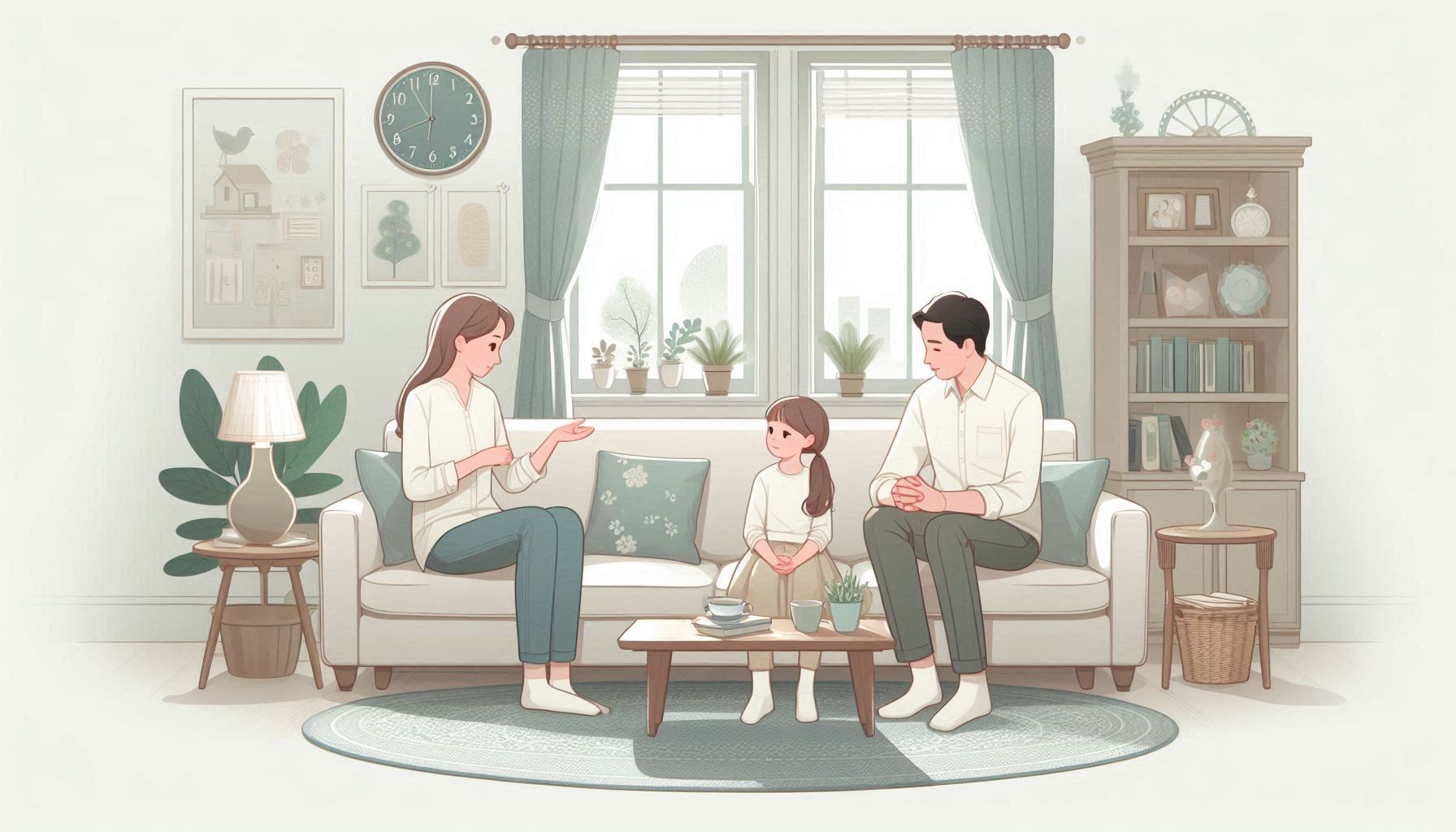子育て中の皆さんお疲れ様です。
子供に用事があって声をかけた時、返事や反応が返ってこない時ありませんか?
聞こえるぐらいの声の大きさで声をかけているのに、反応してくれないと難聴を疑ったり、わざと無視しているかと心配になったり、不安になったりしますよね。
今回は未就学児が話を聞いてくれない理由を解説します。
目次
話しを聞いてくれない理由
早速、子供が話を聞いてくれない理由を解説していきます。
ケース別に解説していますが、反抗期などの理由は内容の位置づけを未就学児としていますので、省いています。
夢中になっていて聞こえない
子供が何かをしている時に声をかけても反応がない時はありませんか?
もしかしたら子供が何かに集中している状態「フロー」や「ゾーン」に入っているかもしれません。
幼少期のこの体験は、子供の集中力を伸ばすうえでとても大切で、目標達成により自身がはぐくまれていきます。
途中で声をかけると集中が途切れてしまうかもしれないので、なるべくそのままにしておいた方がいいとされていますが、日々の生活の中でやらなければならないことや、時間が差し迫っているケースだと難しいですよね。
とはいえ、小学1年生でも集中力が続くのが「15分」程度とされているので、できればそこまで待ってあげられるのが理想的です。
答えにくい質問
声をかける際に、子供が理解しにくい、もしくは答えにくい漠然とした質問をしていませんか?
例えば「今日何があった?」「どうだった?」など主語もなく漠然とした質問をしている場合、ママやパパは子供のことを知りたいと思っているかもしれませんが、子供は「どのように答えたらいいのかわからない」状態になってしまいます。
この場合、返事が返ってこないまでは無くても、「わからない」「たのしかった」など具体的ではなく、そっけないともとれるような返事が返ってきているかもしれません。
返事をしなくても大丈夫だと思っている
何かしてほしいことがあって、子供を呼んでも反応しない時ありませんか?
例えば「脱いだ服を片付けて」や「~とって」など、もしかしたら子供は自分がやらなくても、ママやパパがやってくれると思っているかもしれません。
反応がないと、子供の代わりに自分がやった方が早いから、やってしまっていませんか?
実は子供もその反応を見ていて、「自分が返事をしなくても大丈夫」「自分がやらなくても大丈夫」と考えて、返事や反応をせずにやり過ごそうとしているかもしれません。
子供が聞いてくれる声掛けの方法
どうすれば子供たちは大人の声に反応してくれるのでしょうか。
ここでは、子供たちが反応しやすい対応方法を紹介します。
視界に入るようにする
子供に声をかけるとき、視界に入るようにしてから声をかけてみてください。
そうすることで、「自分に話しかけられている」ことを子供が認識しやすい状況を作ることが出来、返事をしてくれやすくなります。
この時のポイントとしては視界に入り、子供に顔が見えるようにしておくとよりわかりやすくなります。
しっかりと目を合わせる
子供の声をかけるとき、しっかりとアイコンタクトをとるようにしましょう。
大人も、アイコンタクトがあると声をかけらそうなど何となくわかりますよね。
子供も同じで、しっかり目が合ってからだと、こちらに意識を向けてくれやすくなります。
「話始めるぞ」という合図を子供が受け取って、聞く姿勢をとりやすくなりますよね。
スキンシップをする
視界に入ったり、目を合わせようとしても子供が見ていないと、そもそも成立しませんよね。
そんなときは、スキンシップを併用しましょう。
話しかける際に軽いスキンシップをとることで、子供が気が付きやすくなります。
スキンシップはハグなどでもいいですが、「頭をなでる」「肩を叩く」などの軽いもので、子供の注意をこちらに向かせてから話しかけてみましょう。
スキンシップは幸せホルモンである「オキシトシン」の分泌されるため、気持ちを落ち着けたり、ママやパパとの絆を深めるのにも役立つので、子供に注意するときや子供が反発しやすい内容の話をする前などにも効果的です。
名前を呼ぶ
子供に声をかけるとき、名前を呼んでいますか?
しっかりと名前を呼んであげることで、子供も自分が呼ばれている認識をしっかり持てるようになります。
兄弟や姉妹などであれば、上の子を「お兄ちゃん」や「お姉ちゃん」と呼んでいる方も多いと思います。
もしくは「ねぇ」や「ちょっと」など主語をつけずに、昭和のような呼び方をする人もいるかもしれません。
察してほしいなど思うかもしれませんが、誰を呼んでいるのかわかりづらいため、子供も自分が呼ばれていると気が付きにくいかもしれません。
また、名前を呼ぶことで相手の好感度が上がる「ネームコーリング効果」もあるとされているため、名前を呼ぶことは非常に有効な手段です。
とはいえ、強い口調で名前だけを呼ぶのは逆効果になり、「怒られる」と子供が身構えてしまうので、注意が必要です。
子供にも理解できる言葉・答えやすい質問を使う
子供に質問するときに年齢に合わせたわかりやすい言葉や、答えやすい具体的な質問をすることで、子供たちは返事をしやすくなります。
例えば片づけをしてほしい時は「ナイナイしてね」と子供がよく使う言葉に言い換えたり、「今日保育園どうだった?」ではなく「今日保育園で誰と遊んでたのしかった?」など質問の範囲を狭めて、具体的に聞いてみましょう。
場合によっては質問と返事のラリーが多くなり、めんどくさいと感じるかもしれませんが、子供との会話が増えコミュニケーションにもつながります。
何かやってほしい時も同様に「片付けて」ではなく「ブーブーをおもちゃ箱にナイナイでしてほしいな」など年齢に合わせた具体的な指示を出すと効果的です。
その他の対応注意点
上記以外にもママやパパの対応で大切な注意点を紹介します。
無視をそのままにしない
無視や無反応である子供を、そのままにしておくことは非常に危険です。
自分がやった方が早いから、いつまでも動かないからなどの理由で親がやってしまったり、答えなくても大丈夫の成功体験を作ってしまうことで、無視や無反応を悪化させてしまいます。
かといって子供が無視したときに怒って強い口調で言ったり、叱ったり、罰を与えるのも逆効果です。
前述した声掛けをしてみたり、子供に無視されるとどういう気持ちになるのかをしっかり伝えて、無視や無反応がよくないこと、悲しいことだと認識してもらいましょう。
ママやパパも話をしっかり聞く
当たり前のことですが、子供の話をしっかり聞いてくれないママやパパの話を聞くわけがありません。
子供の話をちゃんと聞く姿勢を、親であるママやパパがしっかり子供に見せていくことが大切です。
また、他人に対しての対応も子供たちはしっかり見ています。
たまに外で、横柄な態度や人の話を聞かない人を見かけますが、その子供も他人に対して同様の対応をとるケースが非常に多いです。
親として人の話に耳を傾ける姿勢を子供に見せて、マナーやモラルなどを学ばせましょう。
叱っている時の無反応は要注意
子供を叱っている時に、急に無反応になったり、全然違うことを言ったり、やったりすることがありませんか?
その場合は腹が立つかもしれませんが、要注意です。
この状態は恐怖から「逃避」している可能性があり、簡単に言うと恐怖のキャパシティーを超えて、子供が自分を守るために行っています。
もしも叱っている時に子供がこの状態になったら、一旦話をやめて抱きしめながら怖がらせたことを謝るなど、子供を安心させてあげてください。
子供の叱り方にもしも思うところがあれば、下記の記事も参考にしてみてください。
▶【絶対やっちゃダメ!】子供の心身に悪影響を及ぼすNGな叱り方
まとめ
筆者も子供の無反応に大変苦労しましたが、子供の無視や無反応は、本当に堪えるものがありますよね。
子供の無視や無反応を容認し続けてしまうと、反抗期に差し掛かるとより悪化してしまうため、最悪家庭崩壊にもつながりかねません。
家族でのコミュニケーションが苦痛にならないように、ママやパパも子供の話をしっかり聞き、子供の無視や無反応を減らす対応をしていくのは非常に重要です。
筆者も今回解説した理由を知り、対応方法を試したところ、かなりの割合で反応してくれるようになったのですが、とくにおススメなのはスキンシップを交えることです。
続けていると子供の反応が明らかに変わってきますし、大人側も声をかけるのが楽しくなってきます。
もしも子供の無視や無反応に心当たりがある方は、ぜひ試してみてください。
幼少期からしっかり対応をして、コミュニケーションが自然に取れる環境を整えていきましょう。