子育て中の皆さんお疲れ様です。
子供に接する際にママとパパで、子育て方針が違うなんてことありませんか?
実は日常的に接する保護者で対応が大きく違うと、子供たちはどちらを信じていいかわからなくなり、混乱してしまいます。
でも、ママとパパだって違う人間なんだから仕方ない部分もあると思います。
今回はぜひ話し合ってほしい、子育て方針について解説していきます。
目次
子育て方針の違いってそもそもなに?
「子育て方針の違い」と言ってもいまいちピンとこないと思います。
今回解説する「子育て方針の違い」とは何かを学ばせることや遊ぶものなど、すべてを含め子育ての方針としており、その方針が保護者間で違うことを指しています。
ご自身での体験でもこんなことはありませんか?
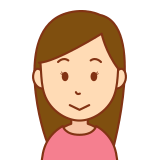
ご飯の前におやつはダメよ。
道路で遊ぶのは危ないから公園で遊んでね。
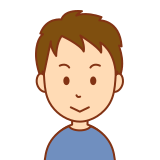
ママこう言っていたけどパパはいいと思うよ
上記のようにママとパパで言っていることが違う、もう一方の方針を子供の前で否定してしまうなどのことを「子育て方針の違い」としています。
子育て方針の違いは何がいけないの?
子育て方針をママやパパがそれぞれ持っていることは、とても良いことですし、むしろまったく同じだとその他の方針を受け入れがたくなり、広い視野をもつきっかけが出来にくくなってしまいます。
では、何が問題なのかというと、「子育て方針の違いを夫婦間で話し合うことをせず、それぞれの方針で子供に伝えてしまう」とことが大きな問題なのです。
ママやパパもそれぞれ理想像や子供への感情、過去の経験から子供への対応を行っているかと思います。
ですが、それぞれが違う方向性のことを言ってしまったら、子供は何が正しいのか判断するのが難しくなってしまいますよね。
例えば大人でも会社に勤めていると先輩や上司などから、それぞれ違う方向性のことを言われて困ったことありませんか?
その場合は役職や実績で判断できますが、家庭においてはそうはいきません。
幼い子供であれば尚のこと難しいでしょう。
子供も人間です。ママとパパで違いがあれば「楽な方」や「自分にとって都合の良い方」「甘い方」によって行くのは当たり前です。
これが続いてしまうと、どちらかのいう方しか信じず、どちらかを嫌うなどの傾向が出てしまいます。
まったく同じ対応をとる必要はありませんが、方針としてはママとパパがぶれすぎないように努める必要があります。
パートナーと子育て方針をまとめるコツ
子育て方針を決めるためにどのようにすればよいのでしょうか。
ここでは、子育て方針を決めるために大切なコツを紹介します。
理想像を語りあう
まず最初にしてほしいのが、子供にどんな大人になってほしいのかなど、ママとパパが持っている理想像を話し合ってください。
お互いがどんな考えを持って子供に接しているのか知ることで、お互いの接し方の違いの理由が見えてきます。
その時、相手を否定するのではなく、なるべく受け入れる姿勢で話し合いましょう。
実際の対応について話し合う
パートナーと理想像について話し合ったら、次は実際の対応についてどうするかを話し合いましょう。
この部分は内容が多岐にわたるため、一度にすべて話すのは難しいので期間を空けて複数回に分けて話し合いましょう。
例えば子供に何か生活や態度、環境の変化があったときや、成長の内容を共有する時、問題が起こった時など節目や些細なきっかけでもいいので、話し合えると理想的です。
子供が独り立ちするまで未来の対応を決めるのは現実的ではありません。
複数回の都度話す内容を下記のように絞って話すのが、おススメです。
必ず理由と背景の掘り下げを行う
話し合いではお互いに過去・現在・未来の対応についてどう思うのか、主張と歩み寄りによって対応を共通認識としていくのが目的ですが、片方の主張を理由や背景も聞かずに一方的に採用することは危険です。
誰しも感情に流されるときがあったり、盲信しているものがあったりするなど、場合によっては後悔することもあるかもしれません。
パートナーの意見が正当に思えても、なぜその対応をするのか「理由」と「背景」を質問しあいましょう。
掘り下げてみると対応も変わってくる可能性があります。
例えばスマートフォンを何歳から持つかであれば、ママとパパが中学生からとお互いの意見が合致していても掘り下げてみると防犯のために、小学生のうちに子供に持たせて、ネットなどはペアレンタルコントロール機能を使っておくなど方針が変わる場合があるため、必ずやってみましょう。
子供の性格や興味を考慮する
子供によって性格や興味を持っていることは様々です。
子育ての方針を決めるうえで子供の性格や興味を無視してしまうと、対応を決めたとしてもうまくいかず、反発されてしまったり、子供やママパパもストレスを抱えてしまうことになります。
例えば性格がおっとりマイペースで朝の支度などに時間がかかるなら、時計を見せながら「長い針がここにくるまでお着換えを終わらせようね」などの対応をしてみる、一人で挑戦したい性格なら「お着換え一人でお願いしてもいい?一人で早くお着換え出来たらママパパすごく助かる」など性格に合わせた対応が出来ますよね。
子供の興味もおもちゃや遊び、習い事を選ぶ際にも役立ちます。
体を動かすのが好きならボールを買って一緒に外で遊んだり、体操や水泳などの習い事をさせてみたり、何かを作るのが好きならブロックやクリエイティブな習い事をさせてみるのもいいかもしれません。
子供が何に興味があるのかはっきりしない場合は下記の記事を読んでいてください。
▶【大人の対応で子供は変わる】子供の興味を引き出し、育てるために知っておきたい大人の対応
パートナー以外の意見も取り入れる
非常に重要なことですが、パートナーとの話し合い以外にも意見を取り入れてみましょう。
パートナーとだけ話し合っていると意見が偏ってしまったり、最新の情報や子供を取り巻く現状に合わない可能性もあるため、より確度をあげるためにやってみてください。
例えばこのサイトのような情報サイト見てみる、子育て中の友人や保育士や保健師の方などに聴いてみるなどしてみましょう。
子育てサロンや相談会に参加してみるのも、いいかもしれませんね。
注意点としては、極端に主義主張が偏っている方の意見は非常に危険です。
絶対に取り入れてはいけないわけではありませんが、子供の身体と心の安全をからならず確保して、子供に押し付けるのではなく、選択できる余地を残してあげてください。
まとめ
子育ての方針についてパートナーと話し合って、共通の認識を持っておくことは非常に大切です。
家庭円満にもなりますし、ママとパパが両方育児に参加しやすくなります。
仕事ばかりで育児はパートナー任せにしてしまっている方も、育児に参加するきっかけになったり、子供のことを考える結果にもなり、もしかしたら変化が起こるかもしれません。
また、子供にとっても両親が一貫した対応をとっていると混乱したり、どちらか一方だけの話しか信じないなんてことも減ってきます。
兎にも角にも大切なことは、パートナーと子供のことについて話をすることです。
膝を突き合わせて会議のようにする必要もなく、リラックスしながらでもご飯を食べながらでも、気軽に話せるようにしていきましょう。

